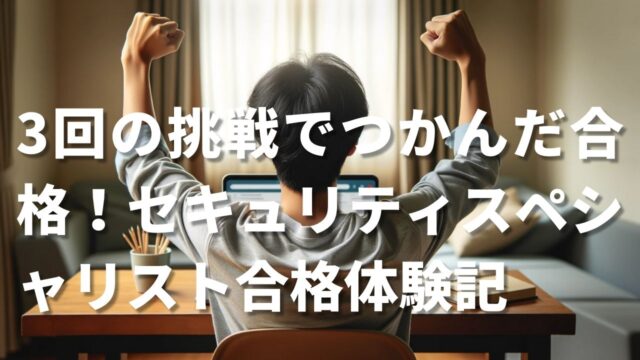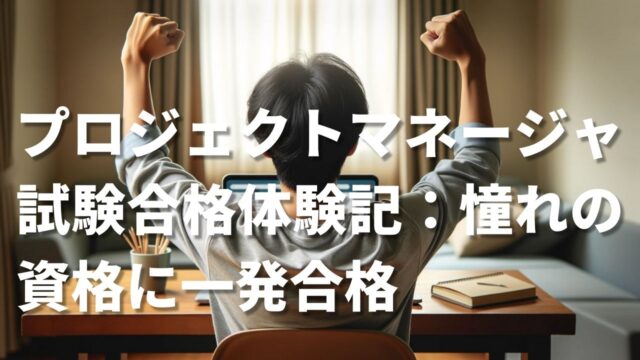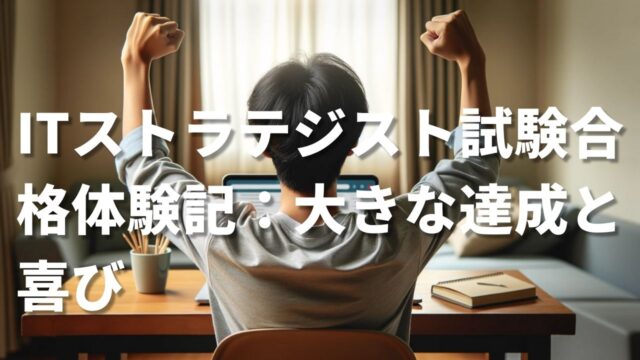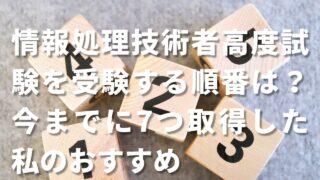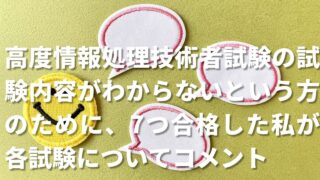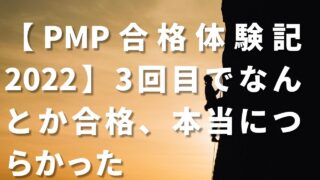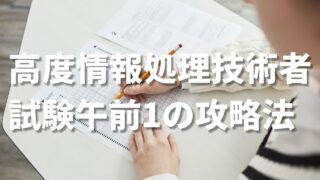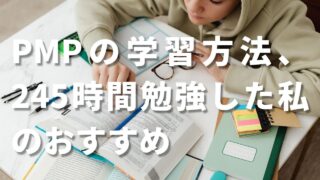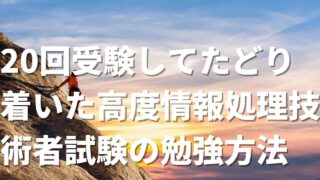情報処理技術者試験を20回以上受験し、高度試験7つに合格したはずけいです。
私が初めて基本情報処理技術者試験を受験してから15年が立ちました。
思い返すと、本当にいろいろなことがあったなと思います。
私が試験に挑戦する過程とその時感じたことを書きました。
情報処理技術者試験を受験している方にとって何か気づきや面白いと思うポイントがあるかもしれません。
かなり長文になってしまったので、流し読みして気になるところだけ読んでいただければと思います。
私の情報処理技術者試験年表
全体像があったほうがわかりやすいと思ったので、私の受験と合格の履歴を年表にしてみました。
| 西暦 | 春試験 | 秋試験 |
|---|---|---|
| 2007年(1年目) | 受験なし | 基本情報:不合格 |
| 2008年(2年目) | 基本情報:不合格 | 基本情報:合格 |
| 2009年(3年目) | 応用情報:合格 | NW:不合格 |
| 2010年(4年目) | DB:不合格 | NW:不合格 |
| 2011年(5年目) | SC:不合格 | NW:不合格 |
| 2012年(6年目) | SC:不合格 | NW:不合格 |
| 2013年(7年目) | SC:合格 | NW:不合格 |
| 2014年(8年目) | DB:不合格 | NW:合格 |
| 2015年(9年目) | DB:不合格 | 受験なし |
| 2016年(10年目) | DB:不合格 | ST:不合格 |
| 2017年(11年目) | DB:不合格 | 受験なし |
| 2018年(12年目) | DB:不合格 | SA:合格 |
| 2019年(13年目) | DB:合格 | 受験なし |
| 2020年(14年目) | コロナで中止 | PM:合格 |
| 2021年(15年目) | ST:合格 | AU:合格 |
それでは、1年目から過去を振り返ってみたいと思います。
1年目:受験スタート、やる気に燃える新入社員

2007年、新入社員として入社し同時に私と情報処理技術者試験の付き合いがスタートしました。
私の入社した会社では、情報処理の資格を取得すると報奨金がもらえ、基本情報、応用情報、高度試験と金額が上がります。
また、毎月の給料にも資格手当が加算され、こちらも上位の資格を取得すると金額が上書きされる仕組みでした。
同期全員が同じところを目指していました。
基本情報処理技術者試験を誰が一番先に取るか競争する感覚もあり、やる気に燃えていました。
私はとある大学の情報系の学部を卒業していましたが、基本情報処理の内容はとても難しく合格するのは大変そうだと感じられました。
この時、高度試験ははるかな高みにある憧れの資格でした。
高度試験に合格して表彰される先輩を見ていつかは自分もと考えていました。
基本情報に苦戦している私が高度資格に合格できるのは40歳くらいになるのではないかと思っていました。
2年目:基本情報に合格
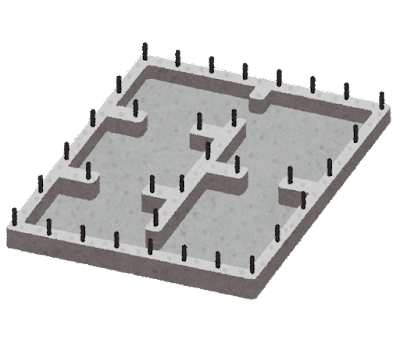
3回目の受験で基本情報処理技術者試験に合格することができました。
同期の中でも取得は早い方でとても誇らしい気持ちでした。
両親も私の合格をとても喜んでくれました。
特に父親は「国家資格だからとても価値がある」と資格を取得するたびにおおげさに誉めてくれ、私の資格取得の原動力の1つとなりました。
資格を取得した時に思ったのは、大学でやってきたことと業務はレベルが違っており、基本情報は業務のレベルだと感じました。
学生の方で基本情報を取得されている方がいるようですが本当にすごいなと感じます。
3年目:応用情報処理技術者に合格

応用情報処理技術者は、基本情報処理技術者と内容はほぼ同じで内容が難しくなった試験という感覚でした。
合格した人から「基本に比べて応用はかなり難しい」と聞いていたので合格まで時間がかかることを覚悟していたのですが、私は一発で合格することができました。
私は、勉強をしているときも、本番でも基本情報と比べてそこまで難しいとは感じませんでした。
基本情報の取得に苦労したので、何回も受験するうちに実力がついていたのかもしれません。
3〜5年目:高度試験への挑戦

応用情報処理技術者に合格した私は、高度試験との長い付き合いを始めることになります。
高度試験は9つありそれぞれがどのような内容の試験なのか、何から受験すれば良いか全くわからない状態でした。
高度試験の1回目はネットワークスペシャリスト試験(NW)を受験しました。
ネットワークの分野に興味があったのと、周りで持っている人が少なかったので「持っていたらレアかもな」と思って受験しました。
意外と手応えがあり、合格まで後2点というところまで迫ることができたので秋試験はNWを受けることにしました。(この選択によって後から地獄を見ることになります。)
次の試験(最初の春試験)はデータベーススペシャリスト試験(DB)を受験しました。
DBは高度試験で最初に受けるというイメージがあり、周りでも持っている人が多かったです。
結果は完全敗北でした。午後2試験のあまりの難しさに心が折れて途中退席してしまいました。
DBに合格できるイメージが全く持てなかったので、翌年はセキュリティスペシャリスト試験(SC)を受験しました。(現在の情報処理安全確保支援士試験です。)
SCは不合格だったものの手応えがあり、そこからは「春:SC」「秋:NW」の組み合わせで受験することにしました。
SCとNWは学習内容で重複している部分が多く、効率的に勉強できるのもいいなと思いました。
勉強時間については主に土日に図書館に行って2〜5時間くらいやっていました。
1日中勉強しようと張り切って図書館に行くのですが、集中力が続かず2時間くらいで帰宅することもあり、その時は自己嫌悪でひどく沈んだ気持ちだったことを覚えています。
土日に勉強するので、プライベートを犠牲にしているという感覚も強くありました。
6〜7年目、セキュリティスペシャリスト試験(SC)に合格

2013年、3回目の挑戦でついにSCに合格することができました。
点数照会のページで合格の文字を見た時は何度もガッツポーズをしました。
一番嬉しかったのは、会社の資格手当が最高額にアップしたことです。社内に掲示もされとても誇らしい気持ちになりました。
高度試験に一つ受かった私はもう一つ取ろうという気持ちを強く持ちました。
理由はSCがデータベーススペシャリスト試験(DB)やネットワークスペシャリスト試験(NW)に比べて1段レベルが低いと感じたからです。
高度資格を持っているというからにはSC以外も欲しいと思いました。
秋試験で受けていたNWは午後2試験がとても難しく、合格の光が全く見えない状態でした。
この頃の勉強法は、過去問よりもテキストを重視する勉強をしていたのですが、今からすると効率はあまり良くないなと感じます。
問題集はテキストをきちんと理解した後に過去問をやるものだと思っていました。
過去問の午後問題は、同じ問題が出るわけではないので何度も同じ問題をやっても仕方がないと考えていました。
プライベートではバイクが趣味になり、週末は出かけたかったので土日は一切勉強しないことに決めました。
嫌でたまらなかった土日の勉強を「やらない」と決めたおかげで気持ちがとても楽になりました。
その代わり、試験期間の平日は毎日勉強することを自分ルールとしました。
最初は仕事が終わった後に勉強していたのですが、疲れて家に帰って勉強するのが辛かったので、毎朝1時間早起きして勉強することにしました。
私は早起きが苦手でどうしても二度寝してしまうので、目覚ましがなったらとにかくベッドから転げ落ちるということをやっていました。
8年目:ネットワークスペシャリスト試験(NW)に合格

2014年、6回目の挑戦でNWに合格することができました。
最初の頃より実力は上がっていたものの、午後2は過去問をやってもよくわからないという状態でした。
あきらめて今回で最後にしようと思って受けた時に合格できました。
「棚からぼたもち」といった感覚でしたが素直に嬉しかったです。
9〜11年目:情報処理技術者試験はもうやめよう
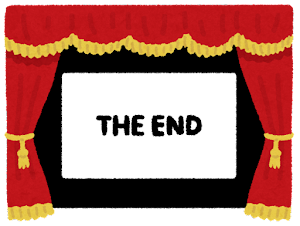
この頃の私は試験を受けることや、勉強することがあまり苦痛ではなくなっていました。
受験が習慣化して、毎年恒例「春と秋の運動会」のような感覚になっていました。
春試験ではデータベーススペシャリスト試験(DB)を受験していましたが、何年も受からない状態が続いていました。
DBには受からない状態でしたが着実に自分の実力が上がって合格に近づいていることがわかりました。
時間さえかければ全ての試験は取得できるという感覚になりました。
一方で、このまま資格を取り続けて良いのかと悩んでもいました。
試験に合格したからと言ってすぐにその仕事ができるようになるわけでもなく、資格を取ってもあまり意味がないのではないかと思ってしまいました。
周りには、プログラミングのスペシャリストや新しい技術をどんどん習得して活躍しているすごい人が何人もいました。
資格の勉強はしていても、最新の技術について勉強不足な自分は「意識低い系エンジニアだな」と感じて焦っていました。
DBに合格したら情報処理技術者試験をやめてもっと実用的なことを勉強しようと思いまいた。
この頃は会社に1時間早く出社して勉強するようにしていました。
寝る時間、起きる時間、出社する時間全てを1時間前倒しすることで勉強に対する抵抗はさらに下がりました。
12〜13年目:システムアーキテクト試験(SA)、データベーススペシャリスト試験(DB)に合格

2018年秋、SAに一発合格することができました。
午前1免除を獲得していたので、何も受けないのはもったいない気がして受けたものでした。
試験はそれほど難しいとは感じませんでした。
「SAは開発のプロジェクトリーダーのための試験だな、(ちょうど開発PLをやっていたので)自分にぴったりな資格だな」と感じました。
2019年春、ついにDBにも合格することができました。6回目の挑戦でした。
あと数点あれば合格できるというのを何度か経験して、とても悔しかったのですが、何度も勉強をし直して挑戦することでDBについては本物の実力がついたと感じています。
14年目:情報処理技術者試験はもうやめよう⇨いや、やっぱり全部取ろう

朝の時間に勉強することの効果を実感し、この習慣は一生続けようと思いました。
一方で、情報処理技術者試験はこれでもうやめようと思いました。
資格をたくさん取っても仕事ができるようになるわけではなく、もっと実用的なことを勉強しないとダメだと思ったからです。
そこからは英語や、機械学習の勉強を初めてみたのですが、明確な目的がなかったこともあり長続きしませんでした。
もう一度考え直した結果、情報処理技術者試験を全て取るまで受け続けようと思いました。
そのように思った理由は3つあります。
1つ目は、高度情報処理を取ることが私の得意なことだと気がついたからです。
たくさん資格をとっていてすごいねと言われることがあり、他の人には難しいが自分にとってはそこまで難しくない、これが得意なことなのだと気づきました。
そのとき読んでいた本に、「苦手なことを克服するよりも得意なことをとことん伸ばすべき」と書いてあってその通りだと思ったからです。
2つ目は、父の言葉です。
ちょうどこの頃父からもらった手紙に書いてあった言葉に次のメッセージが書いてありました。
「何か1つでいい、仕事でも趣味でもいい自信の持てるもの、誇れるものを作って行ってください。きっと人生の支えになります。」
私にとって自信の持てるもの、誇れるものは情報処理の資格をたくさん持っていること以外には思いつきませんでした。
3つ目は、資格取得が意味がないかどうか確かめたかったからです。
山の上に登ってみなければどんな景色が見えるかはわかりません。本当に何もないのか自分で登って確かめてみようと思いました。
高度試験を4つしか持っていない状態で、「資格なんか取っても意味がないよ」とは言えないなとも思いました。
高度試験を全部取得すると決意するのにあたって、最後に1つ意外な難関がありました。
それは、「人からどう思われるか」です。
私の会社では高度試験に合格すると社内に掲示されます。少なくない額の報奨金もいただけます。
「あいつは肩書きばかり集めている」「報奨金目当てでやっている」そんなふうに他人から思われるのではないかと少し怖くなってしまいました。
でも、人の目を気にして自分の挑戦を諦めてしまうのはもったいない、人にどう思われるかより、自分がどう思うかだと考えて覚悟を決めました。
40歳までに全部取ってやろうという目標を立てました。
勉強は土日も含めて毎朝1時間やることに決めました。
14〜15年目:プロジェクトマネージャ試験(PM)、ITストラテジスト試験(ST)、システム監査技術者試験(AU)に連続合格

PM、ST、AUに連続合格することができました。
さすがに出来過ぎ、運が良かったなと思います。
ただ、一か八かというわけではなく、毎回合格できるだけの実力をつけて試験に臨んでいたことも事実です。
今まで何年もかけて取ってきたものが、短期間に3つも取れたのは自分でも思いがけない成果でした。
勉強を始めた初期に比べ勉強をやり続ける力、効率よく進める方法が身についた結果だと感じます。
試験を受けるのをやめようと思っていた時の自分には見えていなかった新しい風景が見えました。
一度は何もないと思った山の頂上へ至る道で早速1つ発見がありました。
残された高度試験はエンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES)、ITサービスマネージャ試験(SM)の2つです。
まだ何かあるんじゃないかとワクワクしながら山を登っています。
最後に
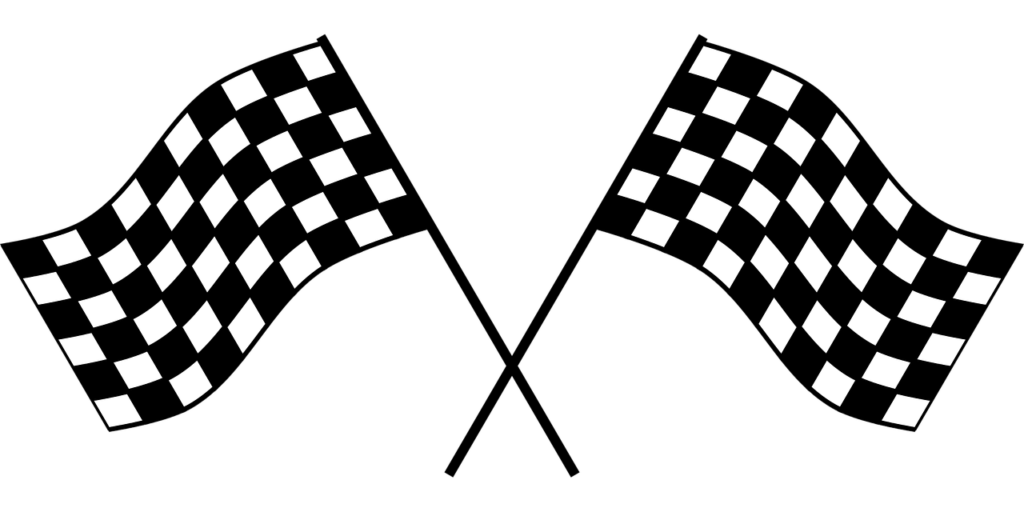
長々と書いてしまいましたが、一番伝えたいことは「やり続けることで見え方が変わったよ」ということです。
私は特別頭が良いわけではなく、大学の偏差値もちょうど50くらいです。
新入社員だった私に、15年後の自分が7つも高度試験に受かっていることを伝えたらきっとびっくりするでしょう。
最初はとても高い壁に見えた高度試験も戦い続けるうちに、頑張れば乗り越えられる壁に変わってきました。
継続することで、かけている力は同じでも、得られる成果は大きくなるということを実感できました。
今、高度資格に合格できなくて悩んでいる方も、もし頑張れるなら努力を続けてみてください。
きっと思わぬ成果が得られると思います。
以上です。ありがとうございました。